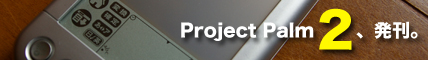
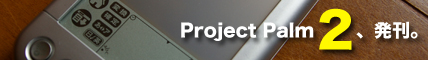
|
PP外伝 |
|
シリコンバレーは遠かった… |
それは、2001年6月のことだった。そう、今から1年半以上も前のことだ。Handspring社の幹部社員で友人のロブ灰谷と、私はメールで「西海岸時間の6月15日の正午にHandspringの本社で待ち合わせる」という約束をした。「プロジェクト・パーム」の取材のためだ。ここから私の、長い長い旅が始まった。「Handspringの本社」は当然アメリカ合衆国の電脳都市Silicon Valleyにある。が、そんな街どころか、私は西海岸などに行ったことがないのだ。ちゃんとたどり着けるだろうか?日本からSilicon Valleyまでおよそ5000マイル!こんな遠い待ち合わせをするのは生まれて初めてなのだ。とっても不安な気持ちを抱きしめたまま、私は成田からサンフランシスコ行きの飛行機に乗った。のちに、Silicon ValleyにはSan Jose空港という地元空港があり便数は少ないながらも日本からの直行便があることを知ったのだが、この時はまだ何にも知らず、とにかくサンフランシスコに向かった。用意したのはHandspring社のサイトから見つけた本社の住所だけ、という心許ない状態で。 サンフランシスコ空港に到着したのは、約束した西海岸時間6月15日の午前11時頃だった。正午まではおよそ1時間。とにかくタクシー乗り場に走り、一台のキャブに飛び乗った。運転手にHandspring社のある「Mountain Viewまで」と告げると、走り始めた車を路肩に止めて「お前はサンフランシスコのタクシー協会のルールを知っているか?」と言い出した。「知らない」と答えると、「長距離の場合、料金は150%になるがいいか?」という。最初はボッタクリかと思って焦ったが、車内にその種の貼り紙が見つかったので、ま、しょうがないと諦めて彼に、ロブとの待ちあわせ場所であるHandspring社の住所を渡した。下手くそな英語のラテン系の運転手は、同社の電話番号も聞いてきて、携帯電話で同社の電話交換手にだいたいの場所を確認してから車を走らせた。「暑くないか?」とかたまに気を使うように言葉をかけてきたが、お互いの英語能力の限界を感じたのか、途中からあまり喋らなくなった。かなり訛りのきつい運転手だったので、それはそれで私も嬉しかった。かなり暑いので窓を閉めてエアコンをガンガンに効かせた方が心地よいのだが、そえだと運転手との間に気まずい空気が流れてしまうので、私は窓を全開にして勢いよく流れ込んでくる外気を顔いっぱいに浴びつつ、窓外の風景を眺めていた。それはそれで心地よかった。 私が乗ったキャブが走り抜ける国道280号線は、ひたすら地味な景色が続く。アメリカっぽい乾いた景色の農村風景に時折工業地帯や近代的なビルが現れる。およそ40キロも走ると、運転手が「近くだ」と呟いて国道を降りた。国道を降りて一般道に出ると確かに、周辺に見える企業の名前はどれもハイテク系企業のものばかりだ。シリコンバレーに来たんだな、と実感する。「もうすぐだから」と言ったきり、車は無機質な静けさの漂うお昼休み直前のハイテク企業団地の中を走り回る。正直、Mountain Viewに到着した時点では時計は11:20ほどだったから、そこまでの道中は快調そのものだったと言える。待ち合わせの時間である12:00まではまだ40分近くもあった。このままなら、早めにMountain Viewの街に到着して、ロブとの待ち合わせ時間まで小粋なカフェでコーヒーでも飲むか?などと考えていた。 ところが、走れど走れど、探しているストリートの名前が見つからない。そこで、キャブの運転手は「もう一度さっきの電話番号を」と言って、目指すHandspring社にもう一度電話をして場所を確認した。「なるほど」みたいな言葉をつぶやいてから、車は自信あり気に再びスピードをあげた。そのあげくに、車は一方通行の道で行き止まりまで来てしまった。「ちくしょう!」と運転手が叫んだ。…もしかして自分は、この運転手に騙されているのか?と不安さえなってきた。と、もっと不安な顔をした運転手が話しかけてきた。「この辺の地図がわからないので、ガススタンドで調べてきてもいいか?」という。わからなきゃ最初から調べといてくれよ、と思いながらも「いいよ、もちろん」と簡単な英語で答えた。ガススタンドから戻ってきた運転手の顔が爽やかだったのでホッとした。「OKだ。もうわかったから!」 ところが、彼が地図で調べてきたストリートを進んでいくと、それまでの工業団地っぽい風景からどんどん普通の住宅街になってくる。そのあげくに、運転手が本当に自信なさそうにこう言った。「この建物がその会社だ。違うかな?」…と、彼が指差したのは、どう見ても民家だ。しかも、近所でもあまり大きくなく、しかも中途半端に古びた民家は、どう見てもドットコム系の企業ビル本社には見えない。明らかにそれは民家だ。誰が見てもどう見てもそれは、思いっきりごくごく普通の民家だ。「これはたぶん違うよ」とだけ私は答えた。すると運転手は「そうだよな。ちくしょう!」とまた呟いて、車を走らせた。そして早口でだいたい次のようなことをまくしたてた。「このストリートは線路を挟んで西と東に分かれているんだ!でも、地図にはそのどっちかとは書いてなかった。だから勘でこっちに来たんだが、逆だったようだ。戻るよ!でも、この反対の場所にある同じ番地のところにあんたの言う会社はあるはずだ!あともうすぐだ!」時計はすでに11:50を回ろうとしていた。約束の時間まであと10分!この街に来てからすでに30分以上を無駄にしたことになる。 実は、アメリカはシリコンバレーまで来たものの、私には大きな不安があった。待ちあわせたロブとは一週間ほど前に「会社のオフィスで12時に!」と約束したきり、連絡が途絶えていたのだ。果してロブは本当に待ってくれているのか?正直不安だったし、彼がメールに書いていた「会社」というのがHandspring社の本社でいいのかどうかも不安だった。もしかしたら本社というのは複数あるのかもしれない。さらには、最終確認をしていない以上、12時を過ぎた場合に、彼がずっとその場所で待っていてくれるのかどうかも心配だった。とにかく、5000マイルも離れた待ち合わせは生まれ初めてなのだ。 再び車は猛スピードで走った。すぐに、彼の言う「ストリートを2つに区切る線路」のところまで来たが、そこには踏み切りがない。運転手は「大丈夫、このもう少し先に踏み切りがあるから」と言って、線路に沿って車を走らせた。ところがだ!走れど走れど踏み切りがない。どこまで行っても、踏み切りが見当たらない。時計の針は11:55をとうに過ぎていた。約束の時間まであと5分!私の暗い表情を感じ取った運転手が「すまない。今度こそ本物だ。ほら、あそこに駅が見えるだろう。あそこには確か踏み切りがあったはずだ!」と。ところが、そこで私は裏切られた。そこには踏切の姿などなかった。さらに言うなら、前を見ても後ろを見ても、見渡す限り踏切など見えないのだ。彼はことさら大きな声で「ちくしょう!」と叫んだが、そう叫びたいのは私の方だった。私は、マジで時間に間に合わなかった場合の悲劇と、その際のタクシー料金(しかも50%増し)のことが心配で、その時のための防御策の意味もあって、ちょっとした芝居を打った。 「もうダメかもしれない。12時までにその会社に着けなかったら、もう一度サンフランシスコ空港まで走ってくれるかい?時間に間に合わないと、私の仕事は失敗になる。そしたら、すぐにでも東京に帰らなければならない」 この嘘が聞いたのか、車の速度は11:57あたりから、信じられない速度まで加速した。もしかしたら時速200キロは越えていたかもしれない。時折、車体がいや〜な音の悲鳴をあげる。高速道でもないので事故るかもしれない速度のまま線路沿いの道を走り、ようやく見つけた踏み切りをこれまた猛スピードで渡りきって、線路の反対側をさっき来た方向へと戻った。幸い対向車もなくて2車線ほどの道を、西海岸の眩しすぎる太陽の中、どんどん飛ばした。そして、運転手が行った。「もうすぐさっきの道の反対側に出る。そしたらそこを左に曲がってしばらく進むと目的の会社だ」と、言った運転手が道を曲がる前に私の方が先に叫んだ。「あれだ!」 まさに線路から曲がってすぐのところにHandspringのロゴマークが見えた。そこが本社ビルと思われた。運転手も気づいて「あ、そう、あれだ」と、車を左折させて横道に入ると、そのまますぐに右折して同社ビル前の正面玄関に滑り込んだ。キキーっとアメリカ映画のようにキャブのブレーキが叫んだ。笑っちゃうぐらいの正確さで時計は12:00をさしていた。運転手は「東京に帰らなくてすんで良かったな」と言いながらも、怖そうな顔のわりにはもともとあまり気が強い方じゃないのか、半べそ状態だった。続いて彼は、急いでトランクから私の旅行鞄を降ろすと、私のためにドアを開けてくれた。 大きな旅行鞄を握りしめた私は運転手に告げた。それは、車中で待ち合わせの時間とともに、もっとも気にしていたことだ。「あのさ、料金についてだけど、この町に着いてからの料金も50%増しなのか?」。彼は顔をうつむかせて「いくらでもいいよ」と言った。そこで、最初の20分間についた料金だけ50%増しにして、残りは普通に換算して、彼があまりにも申し訳なさそうな顔をしているのでチップは普通につけてドル札を渡した。彼は「ありがとう。そして、すまなかった」と言って、車を再び走らせていった。 とにもかくにも私は待ち合わせ場所に着いた。目の前にはHandspring社の小さなロゴが貼り付いた、ペンション風のビルが建っている。私は旅行鞄を引きずりつつ、そのビルの硝子扉を開けて、その中に飛び込んだ。飛び込んだ場所がそのまま受付になっていた。ハハン?って顔で座っていたお姉ちゃんに私は、「東京からPalm Air LineのKICHOが来た。ロブに取り次いで欲しい」と頼んで、受付前のソファで待った。果たしてロブは現れるのか?…と思ったその瞬間、ロブが出てきた。何とか待ち合わせは成功したらしい。久しぶりの再会を果たした私とロブは、ちょっぴり感動の握手をしたが、その次に出た私の一言は… 「ロブさん、申し訳ないんですけど、近くに銀行あります?なかったら、帰りのタクシー代貸して貰えます?」 |
